
都営バス最長距離路線に乗って、あてもなく青梅に向かっていた、とある年の5月半ばの休日。
そのバスで不思議な女と出会い、誘われるままにキネマクラブへと向かったところ、そこは世にも不思議な夢幻のような場所だったのです。
(これは全3編中の第二章です)
Kinema club dunes

「砂の女 -The Woman in the Dunes」
そうか、あの名刺に書いてあった「Dunes」というのは、たしか砂丘という意味だったよな。
砂の女 —もちろんそれが安部公房の代表的な小説で、遠い昔に映画化され、海外で高い評価を得ていることはなんとなく知ってました(観たことはありませんが)。
しかしこのポスターに描かれている「砂の女」の、この忘我の表情のなんと神々しく美しいこと。
そしてさっきのバスで隣り合った女性の、やや鼻にかかった厚みのある声や、首をかしげるようにして僕の目をまっすぐに見上げる視線が、いつの間にかこのポスターと重なってくるのです。
このドアの先には何が僕を待っているんだろう。
僕はなかなかその先に踏み込めずに、しばらくの間、その前に立ちすくんでいました。

こんにちは。やっぱり来てくれたんですね
突然後ろからそう声をかけられて、僕は一瞬心臓が止まるかと思いました。
振り返らずとも、彼女が僕の後ろにいるのはすぐにわかりました。
もちろんあのちょっと鼻にかかった、厚みのある声のせいで。
ここはとても限られた人たちだけのクラブなので、簡単には中に入れないのよ。
彼女はそう言って、古びたドアにはどう考えても不釣り合いな最新のセキュリティシステムのような機械に暗証番号を打ち込みました。
するとロックが解除されるような大げさな音があたりに響き、彼女は僕をドアの中へと導きました。
僕が薄暗い建物の中へ進もうとすると、彼女は待って、と小さく叫び、僕を後ろから羽交い絞めにするように抱きかかえました。

この先には大きな穴があるのよ、そのまま進んだら、真っ逆さまよ
そんなふうに彼女が僕の耳元でささやく声を、とうとう聞いてしまいました。
水で塗り固められた砂の銅像のように、その場で固まってしまった僕からゆっくりと躰を離しながら、彼女は言いました。
ここから先は、私の言うとおりにしてください。
建物の中は、天井の高い広大な空間になっていました。
中には照明施設がなく、天井近くにあるいくつかの窓から天然の光が差し込んでいるだけなので、晴れた昼間でもやや薄暗い感じがしました。
次に目に入ってきたのは、巨大な砂場に掘られたような深く黒々とした穴でした。
その穴のずっと底の方に、半ば砂に埋もれ、今にも崩れ落ちそうな木造の家が1軒建っています。

あそこが「Kinema club dunes」の場所よ。
町の中に黙ってこんなに大きな穴を掘っちゃったので、あまりたくさんの人に言うわけにはいかないのよ。
そう言って彼女は穴の中へと降りる縄梯子を勝手にするすると下って行きました。
高いところが苦手な僕にとっては、こんなところから不安定な縄梯子を使って下に降りるなんてとんでもないことでしたが、梯子の途中から、やや首をかしげ、しかしまっすぐに彼女に見上げられると、意を決してあとに続かざるを得ませんでした。
ここは「砂の女」の世界を忠実に模した場所なの。
ところで、「砂の女」はご存知?
僕が穴の底まで下り終わると、彼女は僕の髪の毛や肩に降りかかっていた砂を手で軽く払いながらそう言いました。

名前は知っていたけど、小説を読んだことも映画を観たこともない
僕がそう答えると、彼女はゆっくり頷いて屋内に僕を誘いました。
「砂の女」とは
都会から、砂丘に住む珍しい昆虫を探しに来た若い教師が、知り合った村人の好意で部落の民家に泊まることになった。
砂地の大きなくぼみにあるその家に、縄梯子を伝って下りてみると、そこには若い寡婦がひとり、住んでいるだけだった。
とどまることなく地上から砂が舞い散ってくるその家で慣れない一晩を過ごし、朝、目覚めてみると昨晩まであったはずの縄梯子がなく、地上に戻ることができなくなっている。
そして家の中では、女がただ顔に砂除けの手拭いをかけただけで、全身に何もまとわずに横たわって眠り込んでいる。
女の躰の上に、滑らかな曲線の形のままに降り積もる、砂。
女を起こし、縄梯子がない理由を聞く男。
しかし、女はそれに答えず、ただ謝るばかり。
女手一つで暮らすことが難しい、過酷な砂丘での生活のため、村人の仕業により、男はここに閉じ込められたのだった。
彼女からそこまでのあらずじを聞いた僕は、ふと気になって古びたドアの隙間から外を見てみます。
そこからでは角度が悪いのでしょうか、さっきまであったはずの縄梯子が見あたりません。
慌てて外に飛び出して、家の周りをぐるりと見回してみましたが、それはもう、どこにもありませんでした。

今日はここに泊まっていきます?
いつの間か僕の後ろに迫っていた彼女が、僕の耳元で、あの、ちょっと鼻にかかったような厚みのある声でささやきました。
渇望

それは、僕もここに閉じ込められてしまう、ということ?
しばらくの間、沈黙がありました。
僕にはそれが、落ちても落ちてもなかなか砂が減らない、大型の砂時計のような長い時間に思えました。
時間の経過とともに、地響きのような音が遠くから聞こえはじめ、それはだんだんと大きくなってくるようでした。
そして突然、どーん、という地震のような大きな揺れがやってきて、屋根の方から何か重いものが降りかかってきたところで、僕は一瞬意識を失ってしまったようでした。
僕が目を覚ましたことに気付くと、砂よ、と彼女は言いました。
さあ、早く砂を掻き出さなければ。
いつの間にか、どこからか大量の砂が降ってきて、砂の女の家を次第に埋めつつありました。
彼女はモンペのような作業着に着替え、頭に砂除けの手拭いをかぶって一心不乱にシャベルで家の中から砂を掻き出していました。
板の間に敷かれたゴザの上で横たわっていた僕の横にも、着替えの作業着と大きなシャベルが用意されています。

掻き出しても掻き出しても、上から砂がどんどん降ってきたらキリがないじゃないか。
これはいつまで続くんだろう?
黙ってみているわけにもいかず、彼女を真似てシャベルを使いながら僕は言いました。

いつまで続くかわからないんですよ。とにかく砂が止まるまで掻き出し続けなければ、家と一緒に埋まっちゃうので、止まるまでは休めないんですよ
彼女の額や首筋から吹き出る汗に、飛び散る砂が次から次へとまとわりつきます。
やがて、水への渇望が激しく湧き上がってきます。
「水は、ないの?」
「すみません、水は、砂が止まらないと手に入らないんです」
砂埃で、喉や鼻の奥がだんだんと塞がっていくような息苦しさを感じます。
このまま窒息死してしまうのではないか、という恐怖が頭をよぎります。

ねえ、君はなぜこんなに苦しい思いをしてまでここにいるの?

それは、あなたに砂が必要だからですよ
彼女は砂をすくっては投げ、すくっては投げ、という作業を機械的に繰り返しながら平然とそう言いました。
「僕に、砂が?」
「そう、あなたに、砂が」
再び、どーん、という音とともに木造の家を軋ませながら乾いた砂が落ちてきて、僕はそれを避けきれずに地面にたたきつけられたようでした。

砂?
それよりなんでこんなに喉が渇く?
それは彼女が無防備に素裸で寝ているからだ。
そんな声でささやくのはやめてくれ、
僕は都バスで最長の路線バスに乗りに来ただけなんだ。。。
やがて僕は口の中に不思議なうるおいを感じて目を覚ましました。

ダメよ、飲み込まないで。最初は口の中の砂を吐き出して
僕の目の前に彼女の顔がありました。
「砂が止まったのよ。水もほら、あっちの方に」
彼女はそう言って土間の水瓶のような入れ物の方へ歩いていきました。

ここにはグラスもないので・・・
彼女は水を含んで戻ってきます。
そしてそのまま横たわっている僕の前にひざまずくと、とても自然に顔を寄せ、僕を潤してくれたのでした。
もっと水がほしい。
彼女の中にある水分を、一滴残らず手に入れたい。
その一心で、僕は彼女を激しく求めはじめたのでした。

<第三章へつづく>
僕の関係する会社です。予約はぜひこちらで!
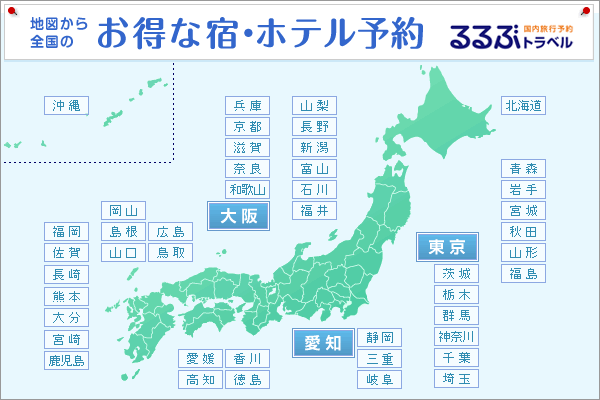



コメント